最近、私の大学が展示している受賞作品群に目を通した際、聴覚障害に関連するデザインが複数の栄誉を獲得していたことに気づきました。しかし、それらを詳しく調べていくうちに、不快感と怒りが込み上げてきました。
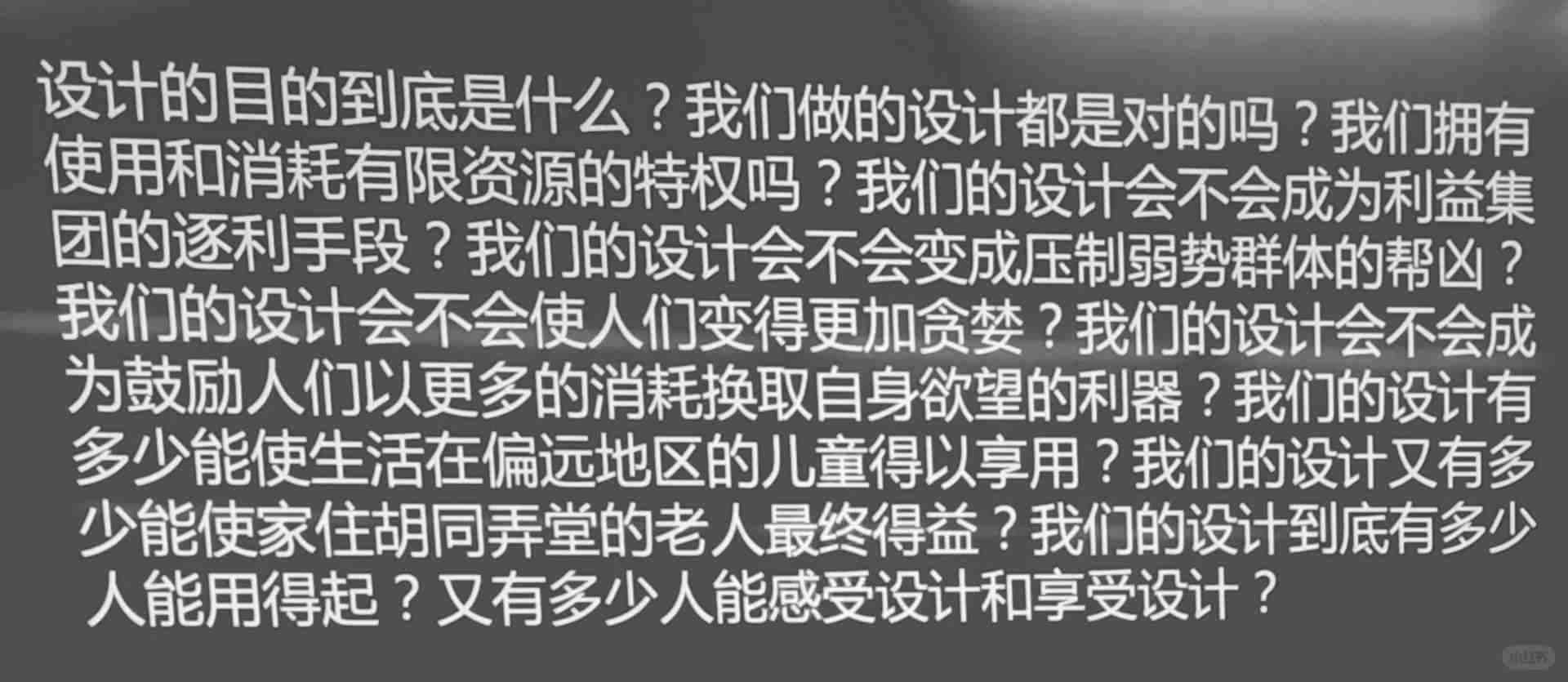
この機関のアクセシビリティに関するアプローチは、私が「パフォーマティブな共感」と呼ぶものに満ちています。それは偽善的な社会意識の見せかけであり、まったく本物ではありません。
本当に腹立たしいのは、これらのプロジェクトに漂う健常者特有の傲慢さです。派手なコンセプトや技術的な洗練さにもかかわらず、聴覚障害者のコミュニティの本質的なニーズを理解していないことが明らかです。私は、障害が単に称賛を得るための都合の良いテーマとして利用されているという疑念を拭い去ることができません。
心が痛むのは、デザインプログラムで共感について教えられ、自分自身も医療プロジェクトに携わってきたにもかかわらず、健常者が障害を持つユーザーの立場に立つことは決してできないということです。私たちの提案には、無意識の優越感が常に含まれています。さらに悪いことに、学校は実際のユーザーグループへのアクセスを提供せず、私たちは仮定のエコーチャンバーの中でデザインすることになります。
教授たちは革新とコンセプトの華麗さに執着し、現実離れした幻想的なアイデアを生み出します。これらは、もし悲劇的でなければ笑えるかもしれません。結果的に、アクセシブルデザインはしばしばただの虚栄心の発露となり、技術力を誇示するための舞台や受賞の切符になりがちです。そして、実際のユーザーとは完全に隔絶された状態で作られています。
この歪んだシステムでは、障害を持つ人々は道具として扱われ、その姿は見えなくなります。彼らの本当の闘いは影に隠され、デザイナーの進歩性を示すための道具に過ぎません。
その記事、とても共感しました。特に「パフォーマティブな共感」の部分は、障害者への無関心や傲慢さが透けて見える気がします。実際のところ、デザイン側の都合で妥協されているケースが少なくないですよね。